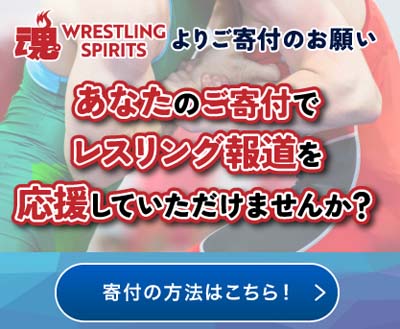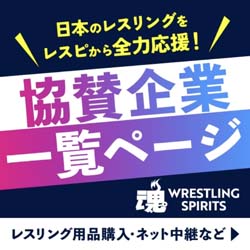【全国少年少女選抜選手権・特集】ベース作りと基本を中心とした指導で10年…AACC
※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(文・撮影=増渕由気子)
 キッズクラブ数が全国一多い東京都で、2001年に発足して今年11年目を迎えるチーム、それが、総合格闘家と総合格闘技の指導者としての顔も持つ阿部裕幸監督(拓大レスリング部OB=写真)が率いるAACCだ。今年も全国少年少女選抜選手権に11人のキッズ選手がエントリーした。
キッズクラブ数が全国一多い東京都で、2001年に発足して今年11年目を迎えるチーム、それが、総合格闘家と総合格闘技の指導者としての顔も持つ阿部裕幸監督(拓大レスリング部OB=写真)が率いるAACCだ。今年も全国少年少女選抜選手権に11人のキッズ選手がエントリーした。
■キッズ・レスリングは将来の土台作り
10年間、同クラブで指導を続けてきた阿部監督の指導方針にブレはなく、「楽しくやる中でのベース作りと基本を中心とした指導」を展開してきた。「僕らの仕事は、高校に預けるまでの土台作りだと思っています。土台が大きければ、その上に載せるものも大きくできるわけですから。僕は、子供たちのレスリングの強さ弱さより、挨拶や感謝、練習に対して手を抜いてないかなどのほうを重視しています」。
日本協会は、キッズレスリングに強くなることだけを求めていない。AACCもまた、レスリングを通した人間教育に重きを置いている。「中学になって、レスリングから離れる子もいます。でも、嫌いで辞めた子でない場合は、その後、『レスリングがやりたくなった』と再び通いだす場合が多いですね」。AACCでは、本格的に競技扱いされる高校、大学とレスリングを続けてもらうために、理想的なレスリングの普及が行われているようだ。
阿部監督は、昨年から2つの新たな挑戦をしている。一つは、「レスリングより体操での体力づくりを目的としたキンダーガーデン(幼稚部)のクラス」を作ったこと。幼稚園、小学校、中学校と3部門に渡る指導を展開し始めた。
選手のファイトを見つめる阿部代表
二つ目は、「指導者同士の交流を深めようと、昨年から4回ほど(他クラブと)懇親会を行っています。クラブチームが数多い東京だからこそ、横のつながりを強化したいなと。ライバルでもありますが、レスリングの仲間でもありますから」。
交流会で、キッズの指導方針などを共有し、合同練習の企画を立てて、実際に実現しているという。子供たちにとっても、試合以外で他クラブの選手と練習ができるので、好評のようだ。
東京は大会の開催地になることが多い。地方のチームは、試合終了と同時に飛行機や電車の時間を気にして慌しく帰るケースがほとんどだが、東京のクラブは試合後に時間があるというメリットがある。このような時間を生かして、今後も定期的に懇親会をしていく予定だ。