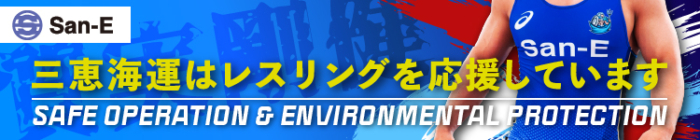【特集】浪速から日本一のチームをつくる! 大体大浪商高・西尾直之監督の挑戦(上)
(文・撮影=布施鋼治)
昨年のインターハイ学校対抗戦で2位となり、今年度の評価も高かった大阪・大体大浪商高。結果は、全国高校選抜大会がベスト8、インターハイが3位。厳しい現実に直面したが、就任から10年をかけてチームを作り上げた西尾直之監督は、しっかりと手ごたえをつかんだ。
神奈川県・磯子工業高校の教員だった同監督が、生まれ育った大阪にUターンする形で大体大浪商高校に赴任したとき、レスリング部には大学生と合わせ8人しかいなかった。西尾は「高校生、大学生とも4人ずつだった。団体戦には、ぎりぎり出ていたと思う」と振り返る。
部員は高校生から始めた初心者ばかり。よほど並外れた才能がない限り、キャリアのある選手に勝つことは難しい。すでに高校レスリング界ではキッズ出身が大手を振って歩いていて、当然のごとく、近畿地区の大会に出ても勝てない日々が続いていた。
打開策として、西尾は小学生や中学生向けの練習会を積極的に開くようにした。現場の雰囲気に接してもらい、のちに進路先のひとつとしての候補に入れてもらおうと思った。効果はあった。「キッズ出身者が入部してくれるようになりました。ちょうど今年の春に大学を卒業した社会人1年目の世代です」
学校法人浪商学園が運営する中高大の一貫校の特性をいかそうと、赴任2年目には中学にもレスリング部を創設した。中学生のときからマットに上がれば、高校がその受け皿になると考えた。「いろいろ声をかけたら、未経験でしたが、現在、日体大に進学している今永望夢という選手が中学校第一号部員として入部してくれました」
奔走したのは西尾だけではなく、姫路GMやOBも積極的に動いてくれた。「大体大浪商高・大体大のOBで、大阪府の高槻市レスリング連盟の河内義雄会長(関連記事)が、母校の再興を願って高槻から2人の選手を送り出してくれました。そのうちの一人が今年のインターハイ125㎏級で準優勝した長谷川大和です」
「また、大学の恩師の福田耕治先生(この8月まで全日本学生連盟会長)が代表を務める茨木市レスリング教室からも選手を送ってくれ、今年、古澤大和が浪商高校初のインターハイ・チャンピオンに輝いてくれました。」
小学校卒業を機にレスリングから離れた西尾監督だったが…
大体大浪商高といえば、高校野球の強豪校として有名だが、かつてはレスリングの強豪校としても知られていた。「去年、近畿大会で団体優勝したのが48年ぶりでした。当時はオリンピック代表(石森宏一=1984年ロサンゼルス大会代表)も出していたし、近畿大会を連覇できるような強豪チームだったんですよ」
そう語る西尾は、キッズ・レスリングが“ちびっ子レスリング”と呼ばれていた時代に、名門・吹田市民教室で汗を流した選手だ。同教室を創設した押立吉男代表の偉大さは、自分が指導者になった現在、あらためて感じると言う。
「押立先生には、カリスマ性みたいなものがあったと思います。子供たちの気持ちを盛り上げるのが上手。当時は全然感じていなかったけど、『君は○○とスパーリングしなさい』というときの対戦者選びが絶妙だったと(周囲が)言いますね。確かに、自分が一番やりたくない相手とよくやらされていましたね」
吹田市民教室に父・西尾秀明さんがコーチとして在籍していたことも大きい。「父は桃山学院大でレスリングを始めたと聞いていますけど、当時、桃山学院大の監督が押立先生だったんです。だから親子二代、押立先生に見てもらったことになります。レスリングを指導しているときの父は厳しかった記憶があります。父親がコーチだと周囲からいろいろ言われることもありましたね」
子供ながらに押立代表からの期待も感じていたが、小学校卒業を機にレスリングから離れた。足が速かったので陸上を始めた。特にやりたい競技だったわけではない。思春期ならではの葛藤だった。もう一度レスリングを始めるきっかけは、大阪市立高校への進学だった。
「いろいろなスポーツをやったけど、その中で、オリンピックを目指そうと思いました。どの種目が一番オリンピックに近いのかと考えたら、レスリングだった」
個人競技だけど、チームを意識させるのが基本理念
西尾の指導方針は、徹底して非暴力を貫く。今では当たり前の話だが、西尾が高校のときには、他校の指導で鉄拳を見ることもまだあった。「でも、高校の恩師である芦田隆治先生(前国際特級審判員)は、一切そういうのがない方だった。おかげで指導者になった僕も手を出すことは一切ありません」
同志社大に進学しても、西尾はレスリングを続けた。転機は大学2年のときに訪れた。芦田監督から「教師になりたい気持ちがちょっとでもあるなら、教員免許を取っておいた方がいい」と薦められた。当時の同志社大では保健体育の免許をとるコースはなかった。商学部に在籍していた西尾は「まずは社会科の教師になろう」と決意し免許を取った。
その後どうやって保健体育の免許を?「卒業後、非常勤の社会科の教師として働きながら、京都教育大に科目等履修生という形で2年ほど通ってとりました」
免許は身を助ける。浪商高では、社会科の教師として採用された。「社会科の教師だったら可能性がある」という話を聞き、チャンスだと思い、試験を受けた。その後採用され、レスリング部の監督就任に至った。
初心者だけで構成されるメンバーで大会に挑んだのは、その前の赴任先である磯子工業高でもそうだった。「部員が18人いたけど、経験者は2人のみ。そうした中、神奈川で開催されたインターハイ(2014年)でベスト4を目標に頑張って、ベスト8まで勝ち進むことができました。千葉裕司顧問(現高体連レスリング専門部部長)と一緒に頑張っていました」
磯子工高での経験も活かし、西尾は浪商レスリング部に新たな基本理念を打ち立てた。「レスリングは個人競技だけど、チームをなるべく意識させたい。個人競技だと、『自分さえよければ、それでいい』という考えになりがち。そういう考えがエスカレートしたら、社会人になってからつまずくことが多い。だったら、チームとしての活動を意識させながら、社会性をはぐくんでもらいたいと思ったんですよ」
その基本理念は、ここ数年の大体大波商の躍進の原動力にもつながっている。