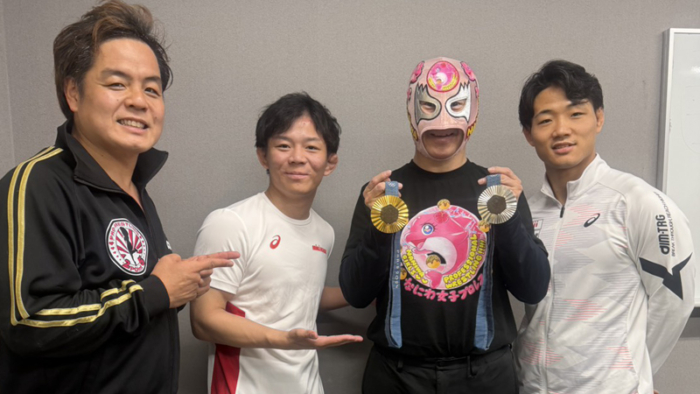【直言! 過去・現在・未来(11)】IOCの会長選びに感じる公明正大さ、レスリング協会・会長選出方法の改革を(上)
(編集長=樋口郁夫)
インターハイなどの執筆に追われ、協会の次期体制についての記事が滞ってしまった。2年はあっという間に経ってしまう。今年実施された国際オリンピック委員会(IOC)と日本オリンピック委員会(JOC)の会長選挙を引き合いに、レスリング協会の世代交代へ向けての提言をさせていただきたい。
まず、協会の会長はどのように決まるか。非常に重要なことだが、レスリング界の現場の人間で、これを正確に言える人は少ないのではないか。総理大臣の決まり方は、中学や高校の社会の授業で学んでいるし、メディアが総選挙の度に報じるので、日本人の多くは知っているだろう(まったく知らなかったら、問題ですよ^^;)。
競技団体の会長選びは、どのような手順で決まるかは知らない人が多いはず。スポーツ界に根強く残る上下関係の中、現場の意見が反映されず、密室で現政権や実力者の根回しによって決まるのが大方の現実だ。したがって、筆者が「会長に立候補する30代、40代の若手、出て来い」と言っても(実際に何人かに声かけしました)、いつ、どのような手続きによって立候補していいのか、分からないのが現実ではないか。
これでは、世代交代は実現しない。旧態依然とした組織の中で現場の声が反映されず、時代の流れについていけない、あるいは変革を好まない高齢者の政権が続くだけ。まず、ここをきっちりと改革する必要がある。
「役員候補者選考委員会」は現政権の“操り委員会”
現在の会長選出の手順は、下記の通り。
(1)役員候補者選考委員会によって理事候補者が選出される。まず7ブロック(北海道・東北、関東、東京、東海・北信越、近畿、中国・四国、九州・沖縄)から各1名、傘下連盟(8団体)から各1名が推薦され、これは無条件に通る。それ以外に、今回の場合、役員候補者選考委員会の指名理事16名(外部理事3名を含む)が推薦され、計31名の理事候補が決まる(規定は24名以上33名以内)。
(2)評議員会が上記の理事候補を承認し、正式な理事となる。
(3)承認された理事による理事会が開催され、互選によって会長が決まる。
「役員候補者選考委員会」は、公平な選考するための委員会のように聞こえるが、どんな選考基準で、どのような手順を経て委員が決まるのか、決まった委員がだれかが明らかにされたことはなかった(今回は理事会後の記者会見で、筆者が公表を求めました=関連記事)。その委員たちが、どんな理由で理事を選考・推薦したかの理由が説明されたことは、一度もない。
委員会の会議の中で、例えば「オリンピックに多くの選手を出した日体大と育英大から1名ずつ出てもらいましょう」「大学最強の山梨学院大からの推薦を受けるべきです」「国際審判から1人選ばないとならないでしょう」「登録の多い高体連から、もう1名出てもらってもいいでしょう」といった話し合いがなされているかと言えば、200%、ありえない。
現政権の意向を受けて理事候補を選出・指名しているのである。今回の役員改選では、現場の人間が「この人、だれ?」と思うであろう人が推薦され、新体制下の専門委員長におさまっている。留任が既定路線だった富山英明会長の意向を受けての選出であることは明白だ(「会長指名理事枠」として数人分を空白にしておき、会長決定後に指名した方がすっきりする)。
トップの意思によって次のトップが決まってきたスポーツ界
そうでなければ、評議員会で理事会のメンバーが承認された直後の理事会で、専務理事らの役員と専門委員長が決まって発表されることはありえない。富山会長の留任と役員・専門委員長は事前の話し合いで決まっており、だれも反対しないことを前提として進んでいる。1人、2人の反対がいても、富山会長の意向を受けた「役員候補者選考委員会」選出の理事の賛成多数で決まる仕組みだ。
富山会長を責めているのではない。他の競技団体も同じようなもので、スポーツ界はそのやり方がずっと続いていた。
2019年6月のJOC理事会では、自薦の会長立候補者が皆無で、山下泰裕氏が他薦され、無投票で決定。すると、その直後に(直後にですよ!)「就任のあいさつ」のコピーが配られたそうだ。自ら立候補しなかった山下・新会長の「就任のあいさつ」が、なぜコピーされていたのか。出来レースなのである! 良識ある理事は、その茶番ぶりを皮肉った。
東京オリンピック組織委員会の森喜朗会長が「女性がたくさん入っている会議は時間かかる」の発言で引責辞任することになった際、後任に川淵三郎氏(Jリーグ初代チェアマン)を指名。川淵氏も承諾し、森氏を相談役にすることを口にしたが、政府筋から「引責辞任する人が後任を指名し、組織に残るのはおかしい」とのまっとうなクレームが入り、白紙に戻った。この例に象徴されるように、日本のスポーツ界は厳然たる上下関係の中で、トップの意思によって次のトップが決まるのが常だった。
表向きは「役員候補者選考委員会」「理事会の互選」など公平に行われているように装っているが、権力者によって事前に99%以上決まっているのが、競技団体の会長選びの実態。民意がまったく反映されない中で行われてきた。
スポーツ界に新たな動き、JOCが選挙で会長を決めた
こう書くと、「各ブロックと傘下連盟から理事が出ている。民意の反映だ」という人が出てくるかもしれない。
ならば、各都道府県協会と傘下連盟の方々にお聞きしたい。「ウチの組織には悪しき上下関係はなく、若手がしっかりと意見を言えて、ばりばり活動しています」と、自信を持って言える人が何人いるのでしょうか? 皆無ではないと思うが、多くの組織が「50歳は洟(鼻)たれ小僧」として、古参役員が大手をふるっているのではないか。
※「50歳は洟(鼻)たれ小僧」=渋沢栄一の名言。50歳は成長途上で、年齢にとらわれず常に向上心を持って生きることの大切さを教えた言葉。転じて、「50歳の若造は生意気言うな」という意味で使われることも多い。本文では、本来の意味から外れますが、後者の意味で使っています。
スポーツ庁が定めた「理事の任期は10年まで」のガバナンスコードと、日本協会の「理事就任時70歳未満」の規定は、協会本体だけでなく、傘下連盟と都道府県協会にも適用するべきである。そうでなければ、レスリング界の世代交代は、いつまでたっても進展しない。
そんなスポーツ界に、新たな動きが出てきたのも事実。6月のJOCの役員改選は、初めて選挙によって会長選びが行われた。