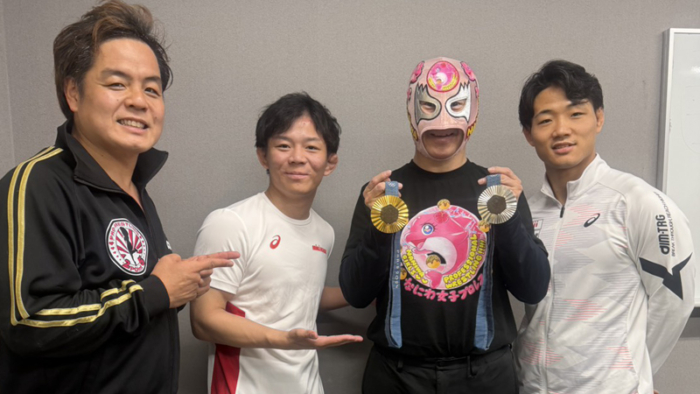【2024年全国中学選抜U15選手権・対談】U15が加わって第15回を迎えた大会、今後のビジョンは?
※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。
2010年にスタートした東京都知事杯全国中学選抜選手権(2022年から大会名に「U15」が加わった)。今年で第15回を迎え、6月の沼尻杯全国中学生選手権とともに、中学生の2大全国大会として定着した。主管する東京都協会の古里光弘理事長と、大会運営の実務を支えてきた高橋尚代事務局次長に、ここまでを振り返ってもらい、今後の展望を話してもらった。(12月1日、東京・駒沢屋内球技場)
--2010年に始まったこの大会も、15回目を迎えました。スタートのきっかけは何だったのでしょうか?
古里 当時、東京都協会が菊池清治会長だった時代です。中学生の全国大会が年に1回しかなかったので、もうひとつ大会あった方がいい、という声が高まっていました。全国大会と区別するため、中学3年生の早生まれ(1~3月生まれ)の選手と小学校6年生の遅生まれ(4~12月生まれ)の選手を対象とし、小学生から中学生へつなげるための大会という位置づけを考えました。
--今でいうU15、U13のカテゴリーですね。
古里 そうです。しかし、小学生と中学生を一緒にやることに問題が出てきました。
高橋 ルールが違うということで、当時はキッズ(小学生)の指導者が対応できない、という面もあったと聞いています。
古里 日本協会からもストップがかかりました。しかし現在、U13・U15という大会ができているわけで、私達は時代を先取りしたわけですよ(笑)。
--第1回大会の参加選手が男子262選手、女子59選手(同年6月の全国中学生選手権の参加選手が男子372選手、女子117選手)。今年は男子490選手、女子161選手。完全に中学生の二大大会として定着しましたね。
高橋 キッズの場合、全国のあちこちで大会があり、数多くの大会に参加することができます。そうした大会で中学生の部を設けているケースもありますが、出場選手は決して多くはなく、中学生選手に出場機会を与えたい、という目的を果たすべきものだったのではないかと思います。
古里 高校は、JOCジュニアオリンピックを含めると5つの全国大会があります。年間1大会、というのは少なかったですね。
高橋 全国中学生選手権でいい成績を残せなかった選手にとって、「秋にもう一度頑張ろう」というモチべーションにつながると思いますし、実際に、この大会で精いっぱい持てる力を発揮できて卒業できたという選手もいたと聞いています。今では貴重な大会になっていると思います。
他に先駆けて行ったショーアップ、魅せる工夫にも尽力
--最初は、東京都協会が「全国」という名前の大会を新たにスタートすることに、全国中学生連盟に抵抗の声があった、とも伝わっていますが…。
古里 そう思う人もいたかもしれませんが、表だってはなかったですね。
高橋 そんな中、始まった本大会ですが、当時のスタッフで考えだしたアイデアが決勝セレモニーとしての演出でした。決勝進出の選手はファイナリストと称されて揃いの赤・青Tシャツを着る。各試合ごとに一人ずつ音楽とともに入場し、各選手と審判を紹介するという形式を早々に取り入れてやってきました。
その後、全国中学生選手権でも同じような形を取り上げていただいたり、決勝選手が一斉に入場する形式にしたり、表彰式にも演出を入れたり…。時代に沿って形を変えたりしていますが、選手のモチベーションアップにつながり思い出に残る経験になるよう、今後も状況に合わせて大会を盛り上げていけたら良いと思っています。
古里 新しい大会ということで、大会運営に対する日本協会からの補助金はなかったんです。ですから東京都協会が努力して大会を立ち上げ、開催を続けたという面はあります。
--選手からの出場料(6,000円×651選手=390万6,000円)だけでは、運営できない、と。
古里 できないですね。多くの企業に協賛していただいている反面、多くのみなさんが手弁当、ボランティアで協力していただいている事実もあります。
高橋 はい。細かいところですが、消耗品・飲料等を減らしたり、備品の使い方を見直すなど、節約の努力もしています。
--大学では、経費削減としてパンフレットをデジタル化して印刷代を減らしています。
高橋 実は今回、考えていました。 ただ、中学生くらいまでは、パンフレットが大会出場の貴重な記念品になっているのではないか、という声もいただき、さらには第15回の記念大会ということもあり従来通りとしました。
古里 私達の世代は、やはり冊子パンフレットですね。
高橋 デジタルにする場合、協賛していただいている企業様からの同意をいただかないとなりませんし、オンラインの場合も、バナーを含めて広告に関して一概に決められない点からも今回は見送りました。 一方で、そのことだけが冊子パンフレットを続ける理由にはなりませんから、今後の課題となると思います。
パソコン前でチャレンジの場面も見られるが…
--ショーアップされた入場もそうですが、多くの面でプログレッシブな運営を感じます。今大会では、チャレンジの際の映像がネット中継にも映るシステムを採用されましたね。これまでは、チャレンジの動画までは視聴できず、中継を見ている人にとって何が何だか分からないうちに判定が下されていた。世界レスリング連盟(UWW)のネット中継でも、チャレンジの動画までは映りません。
高橋 配信による中継は、今は専門家に委ねています。ご担当者の努力の積み重ねにより、遠方の保護者・親戚、先輩・後輩、応援してくれている地元の人たち、興味をもっていただいている一般の方等々に観ていただけるものとして、また、コロナ禍における無観客開催等の時期を経て、完全に定着したものになっています。
しかしながら、判定面で言うと、どこまで映像として配信していいのか、という声も届いています。UWWルールでは「会場全体から見える大型スクリーン(1マットに最低1台)に試合の映像を映し出す義務がある」とありますが、ネット中継にまでは言及されていない、とお聞きしたり、中継されることで、参加依頼を承諾する審判が少なくなることにつながっては困ります。ただ、大会運営を含め包括的にブラッシュアップされていけたらいいな、と願うばかりです。
--今もそうか分かりませんが、プロ野球では、微妙なシーンは混乱が起きる可能性があるので、球場のビジョンに絶対に映さない、という慣例があるみたいですね。
高橋 ただ、今は多くの人が観客席から動画で撮影していますので、そこまで考えなくてもいいかな、とは思いますけど。
「U15」の大会なら、高校1年生の早生まれも出られるはずだが…
--大会の今後のビジョンはいかがでしょうか?
古里 昨年からU15の大会(U15アジア選手権代表選考会)とU13の大会が始まり、この世代の振興がいっそう望まれると思います。小学生と中学生をつなげることで、競技人口の増加につなげられればいいと思います。
--2年前から大会名に「U15」という名前がつきました。U15なら高校1年生の早生まれも出られるわけです。今後、高校1年生の早生まれの選手も参加させる可能性もあるのでしょうか。それとも中学生の2大大会としてやっていきたいのでしょうか?
高橋 都協会の理事からは、U15でグレコローマンが始まることを受け、大会名にU15がついているということで、開催経費の問題はまず別にしても、「グレコローマンを実施したらよいのでは?」という意見が出ています。それはその通りと考えています。U15のカテゴリーを守りながら大会の開催ができたら良いと思います。
古里 レスリング人口を増やすためなら、U15としてグレコローマンを含めてやった方がいいでしょう。それによって中学と高校とで接点ができ、新たな展開ができると思います。これまで、中学生の高校進学につながる点でも意義のあった本大会の存在が、U15になることでいっそう確固たるものになると思います。
高橋 一方で、思いとしては、中学生だけの大会を維持していく必要性があるのではないか、と感じています。
--中学で部活動からクラブ活動への移行が現実のものとなりつつあり、いずれ高校もそうなるかもしれません。そうなると、U13、U15というカテゴリーが主流になるのかな、と思います。20年後、30年後は、中学生大会やインターハイ、といった大会は存在しなくなるかもしれませんね。
古里 この大会も、近い将来、年齢区分が変わるかもしれませんね。
--来年もこの時期でいいのでしょうか? コロナが収束し、外国人の来日が増えて国内のホテルが高騰、少しでも早くに宿を押さえたい、という声があります。
高橋 来年はデフリンピックの関係で、12月の第1週の週末になる予定です。