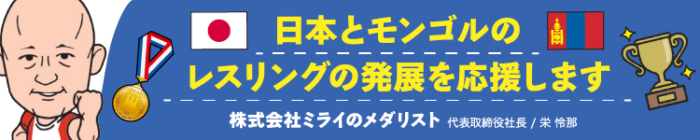《取材日記》新鮮だった石井亜海選手のウィニングラン…9月18日(木)・19日(金)
(文=樋口郁夫)
《9月11・12日》 《9月13日》 《9月14日》 《9月15~17日》 《9月18~19日》 《9月20~21日》
【9月18日(木)】
男子グレコローマンがスタート。前日は女子だけだったので会場にいなかったイラン応援団が戻り、プップッププ-・プップの“ラッパ応援”が復活。会場のにぎやかさが戻ってきた。地元のクロアチアも、フリースタイルよりグレコローマンの方が盛んな国。会場のボルテージは、これまでより上のような気がする。
第2セッションでは、女子のファイナルが行われ、68kg級で3位決定戦に勝ったケネディ・ブレーズ(これまで「ブレーデス」と表記してきましたが、保高カメラマンが「ブレーズ」と発音する旨をゲットしたので、そう表記します)が、3位決定戦の試合が終わると、フロア出口でファンからの記念撮影攻めに遭いました。
ファンがフロアに下りてくるほどの人気。スタッフがやってきてファンを観客席に戻します。日本なら、たいてい、ここで終わり、選手は控え室へ向かうでしょうが、ブレーズは観客席へ入り、そこでファンサービス。2ショット写真などが終わりません。
ここまでファンと親しむ選手も珍しいのではないでしょうか? まあ、米国の選手というのは「プロ」なんでしょうね。いいことだと思います。何よりも強さを求めるのがアマ、強さもさることながら人気や稼ぎも同様に考えるのがプロ。米国のトップ選手は、強さを求める一方、人気獲得も考えているのではないでしょうか。それとも性格的なものでしょうか。
人気のないスポーツは、すたれるんです。アマチュアと言えども、強さだけで記事を書いてもらう時代は、とっくに終わっています。というより、プロアマ・オープンから35年近くが経ちました。レスリングの場合、世界選手権や大陸選手権は、出場することでギャラ(ファイトマネー)は出ませんし、賞金もありません。いわば、「アマチュア」の大会として残っています。
一方、賞金の出る大会はありますし、米国やロシアで行われているスペシャルイベントのように、出るだけでギャラが出て、勝てば賞金が出る大会も存在します。金を関係なしにして強さを決める世界選手権・大陸選手権、そしてオリンピックは、今のまま残ってほしいと思いますが、それ以外では金を稼げるスポーツになっていってほしいと思います。
レスリング選手は(もちろん、トップ選手になってからですが)、人気と金を稼ぐことを念頭において行動するべきかな、と思います。それが、レスリングをメジャー競技に変えていく方法のひとつだと思います。
その68kg級決勝で勝った石井亜海選手。ウィニングランは、見慣れたウィニングランではありませんでした。日の丸を片手に持ち、マットを全速力で1周。オリジナルなウィニングランは新鮮に見えました。保高カメラマンに「これから、流行るかな?」と話しかけてみると、「国旗に対して、その国の考え方があるから…」といった答え。
確かに、そうかもしれません。日本は国旗や国歌に対して「敬う(うやまう)」までの気持ちを持っている人は少ないと思います。国によっては「聖なるもの」であり、片手で国旗を振り回すことは、戦前の日本に存在した「不敬罪」に問われるかもしれません。
かつて、試合前に暴れるだけ暴れたタイガー・ジェット・シンが、インドの国歌が流れると(当時、タイトルマッチは両国の国旗が掲揚され、国歌が流れました)、おとなしくなり、国旗に向かってお祈りしていたシーンが思い出されました。私の日記って、必ずプロレスものが出てきますね^^
表彰式で国歌が流れるとき、独自のパフォーマンスをしたら、日本でも大ひんしゅくですね。国旗に対して忠誠を尽くす国の人は、やはりこのウィニングランはできないかな、と思いました。
そのあとの72kg級では、ウクライナのアラ・ベリンスカが優勝。戦禍のまっただ中の同国に希望を灯しました。フェイスブックのメッセージのやりとりが続いているウクライナのタチアナ・コマルニチカヤ・コーチ(1997年世界選手権で、取材に来ていた東京スポーツは「そんなに見つめられたら、困るニチカヤ」との説明をつけていたほどの美人レスラーでした)に、「Вітаю, ви – надія України.(おめでとう。ウクライナの希望だね)」とのメッセージと写真を送ると、「дякую(ありがとう)」という返信。
今でもキーウに住んでいて、この数日後には「キーウへの大規模空襲で4人が死亡しました」と投稿していました。本当に、1日も早く紛争が終わってほしい!
【9月19日(金)】
9月19日は、だれの誕生日でしょうか? 職業柄、選手の誕生日はけっこう覚える方だと思います。記録は破られましたが、不世出のレスラー、アレクサンダー・カレリン(ロシア)で、この日と「2月20日」は死ぬまで忘れないでしょう(私にとっての最大のスターであり、私の人生をつくってくれた「燃える闘魂」のプロレスラーです)。
カレリンも58歳。世界レスリング連盟(UWW)には入ってきません。2006年世界選手権(中国)のとき、観客席にいたカレリンに東京スポーツのA・N記者とともに突撃インタビュー(片言の英語同士でしたが)。「政治的な活動は嫌いだ。あそこ(当時FILAの役員席)に入ることはない」と言っていました。その通りの人生ですね。
話を大会に戻しますが、第1セッションでは、日本選手全員が初戦か2回戦で敗退。記者席から取材エリアの50段の階段の昇り降りの数も少なくなりました。最終的に敗者復活戦に回れないことになり、翌日のファイナルに日本選手の出場はないことが決まりました。晴れ舞台で勝ち進んでほしい、という気持ちは十分ですが、一方で、この頃になると疲れもかなりたまっているので、女子のときのようなハードさから解放されることに、ホッとする気持ちを感じるのも事実です。
忙しい方がいい、でも、体を休めるのはありがたい、という状況です。昨夜、保高カメラマンは会場内にあるマッサージに行ったとか。9日間連続で働く(しかも長時間労働)スタッフや報道陣のため、こういうサービスがあるのでしょう。有料であっても、必要なことだと思います。

▲撮影日時は不明(スマホには記録されているでしょうけど)。周囲の記者やカメラマンがいなくなったあとも作業をする保高幸子カメラマン。宿舎に帰ってからも続きます。ワーキングホリックになってはいけないと思いつつ、レスリング・オタクは、そうなってしまうのです^^;
9日間連続でやる場合、主催者にお願いしたいのは、仮眠室の設置です。第1セッションと第2セッションの間、短くても1時間半、長いときで3時間以上はあります。横になって体を休めたい、と思うのは記者、カメラマンの共通の思いでしょう。今回はホテルと宿舎が徒歩3分ですから、私は1回、布施さんは2回か3回、帰って横になり疲労回復に努めましたが、車移動が必要なホテルなら、時間にもよりますが、そんな気持ちにはならないと思います。
一度、観客席に横になってうたた寝をしました。イスとイスの間に手すりがないからできましたが、凸凹はあって、そこが背中に当たって痛かったです(それでも意識がなくなるほど寝込んでしまうのですから、疲れていますよね)。会場内のマッサージの値段を聞いたら、日本と同じくらい。それなら、残りの日を頑張り、帰国してから行った方がいいと考え、私は行きませんでした。あと少し、頑張ろう!
第2セッションは、日下尚選手と吉田泰造選手が出場。77kg級の決勝(日下選手出場)があって、そのあと82kg級の3位決定戦(吉田選手出場)。こういう組み合わせ、困るんですよね^^; 試合後のインタビューと次の試合が重なってしまいますから。しかし、間に55kg級の表彰式があることが分かり、何とかなるかな、と。
日下選手が負けたこともあり、短めのインタビューで終了(負けて落ち込んでいるときに、長々とインタビューするわけにはいきません。日下選手は、きちんと答えてくれましたけど、こういうときは、気をきかせて早めに切り上げるものです)。すぐに撮影エリアへ向かうと、まだ55kg級の表彰式をやっていました。
吉田選手は勝って銅メダルを確保。「19歳4ヶ月26日」で(【記録】の記事で、当初、「16日」と書いてしまいましたね。「26日」が正しい記録です)、日本男子最年少の世界選手権のメダル獲得。高田裕司・元日本協会専務理事の「19歳6ヶ月20日」の記録を57年ぶりに更新しました。もっとも、当時は私のような記録オタクはいなかったので、それが日本男子最年少だったとは知らなかったでしょう。
この種の記録って、けっこう選手のモチベーションになっていることを感じます。吉田選手も以前、「史上初とか、歴代1位とか、好きなんです」という意味のことを言っていました。そのためにも、こうした記録、しっかり蓄積していきたいと思いますけど、私もいつかは引退します。この種の記録を継承してくれる記録オタク、出てきてほしいです。
《続く》