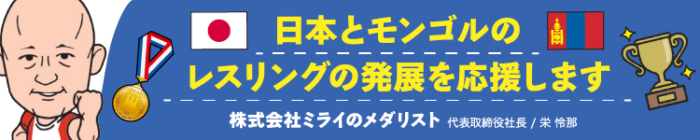【直言! 過去・現在・未来(12)】画期的なUWWの国際会議だが、日本は蚊帳(かや)の外! 英会話への意識を高めてほしい
(編集長=樋口郁夫)
パリ・オリンピック後の初の世界選手権が間もなく始まる。エネルギー充電で休養している選手もいるので、まだ世界のトップ選手がそろうわけではないが、ロサンゼルス・オリンピックへ向けての世界の闘いが本格化する。
今回の世界選手権では、世界のレスリング界にとって画期的なイベントが並行して行われる。「UWW世界カンファレス」で、往年の名選手や世界レスリング連盟(UWW)の重鎮・スペシャリストが参加して講演やパネルディスカッションを行い、世界のレスリング界の発展に寄与しようという試みだ。
世界のレスリング界は、はるか以前は一部の権力者が「私物化している」と言っていいような一面があった。ルールほか多くの物ごとが、会議ではなく一方的に決められ、ときにルールさえ曲げて順位が決まった。
UWWの前身の国際レスリング連盟(FILA)理事だった日本協会の八田一朗会長がFILAの金の不正を追及すると、その直後の1968年メキシコ・オリンピックでは、徹底した“日本つぶしの判定”が横行(ビデオ判定などない時代だったので、かなりひどいこともあったようだ。それでも日本は金4個を取ったのだから、すごい時代だった)。同氏は次の選挙で落選した。
だが、独裁が認められない時代の流れのほか、ネットの時代になって各国間のコミュニケーションがしっかりと取られるようになり、正常化へ向かった。ルール改正にしても、いくつかの大会でテストを実施。各国からの意見を集約してから正式に変更。ビデオの発達によって“意図的な誤審”はできなくなり、組織が成熟してきた。
通訳付きの会議出席は、議論に参加できない!
発展のため、世界の意見を集約しようという試みは、UWWの姿勢として高く評価できる。ただ、残年なことは、このカンファレンスに参加する日本人は、UWWコーチ委員のメンバーである谷岡郁子・日本協会名誉副会長、ただ一人ということ。パリ・オリンピックで金メダル8個を取り、他国を大きく引き離して“世界のトップ”を見せつけただけに、寂しい現実と言える。
原因のひとつは「言葉」だ。カンファレンスで交わされる言葉は英語。通訳もつくと思うが、英語で普通にやりとりができないと、どうしても国際会議には参加しづらい。それは、UWWのメディア・コミッションのメンバーでもある筆者が、肌で感じたことでもある。
これまで行われたメディア・コミッションの会議では、日本協会のA・Tさんや、20年以上前に国士舘大でコーチをやっていたビル・メイさん(元UWWウェブサイト記者)、現在のUWWウェブサイトの記事を書いているケネス・マランツさん(読売新聞勤務)に通訳をお願いして出席してきた。日本語が普通に話せ、レスリング用語も熟知している人がついてくれても、それでは“会議に参加できない”のである。
例えば私への問いかけがあって、通訳がそれを私に伝える。私の答を通訳が訳して話すと、そこに何秒間、長いときで10秒近くの空白が生じる。この空白が会議の流れを壊してしまう。熱い議論をストップしてしまうことに、肩身の狭さを感じることばかりだった。
会議は、街のケンカとは違うのだから、感情的にならず冷静に進めるべきだが、ときに本心をぶつけあう意見の衝突も必要。そうした中から新しい方向性が見てくる。通訳つきでは、熱い議論ができない。
中途半端な英会話力なら、通訳が必要だが…
以前、ある人から「中途半端な英会話力なら、通訳をつけて正しく理解するべきだ」と言われたことがあり、それもそうかな、と思った。間違ってはないが、私は「通訳付きでは本当の意味で会議に参加できない」と訴えたい。
実は、私も「月刊レスリング」の仕事をやるようになって英会話の必要性を感じ、駅前留学(若い人は、何のことか分からないですよね^^)に通ったこともある。英語を話すセルゲイ・ベログラゾフ氏(ロシア)が全日本チームのコーチにいて、年に5回以上、遠征に同行していたので、ブロークン英語とはいえ、かなりやりとりできたが(それでも会議に参加できるレベルには遠かった。セルゲイ・コーチもネイティブでないから、話ができたのだと思うが)、それも途切れ、英会話力は衰えてしまった。
同時通訳がついても同じだと思う。同時通訳は非常に疲れる仕事なので、一回について20分が限度らしい。2時間、3時間の会議なら、何人用意しなければならないのか。ギャラも高いし、レスリング用語を熟知した同時通訳など、そうそういるものではない。
「生まれ変わったら」という話はマイナス思考なので考えることは少ないが、記事の流れで書かせてもらうなら、過去に戻って人生をやり直せることがあれば、学生時代に海外に留学し、ネイティブの人と会議ができるくらいに英会話力をつけたと思う。
国際舞台での日本人不在の解消を
UWWに日本人理事がいなくなって7年が経つ。昨年のパリ・オリンピックでは、セーヌ川に浮かぶ船舶で連日の試合後にUWWの懇親会が行われ、UWWから取材カードをもらって大会に参加していた私達に「金メダリストを連れて来られないか」との打診があった。保高幸子カメラマンが選手に声をかけてくれ、3日間だけだったが、試合後の夜遅い時間にもかかわらず、何人かの選手が足を運んでくれた(終わって私達が宿に着いたのは深夜2時とか3時でしたね。それで朝は10時に会場へ。疲れた~)。
懇親会に彩りを添えてくれたことに、ネナド・ラロビッチ会長はとても喜んでくれた。福田富昭・前日本協会会長がUWW副会長に在任していた時代なら、福田副会長を通じて打診があり、同副会長が選手に声をかけ、もっと多くの選手を連れてきて、日本の存在をアピールできたのではないか。
今年3月に行われたUWWアジア連盟の総会でも、日本人立候補者が落選。こちらでも理事不在となり、日本はいよいよ国際社会から孤立する状態となった。マットの上での強化だけではなく、ロビー外交の面で力を取り戻してほしい。
そのために必要なことは、英会話力。これは日本にいて仕事をしていては、なかなか身につくことではなく、まして会議でやりとりできるレベルになるのは不可能に近いと思う。海外に目を向ける学生や、海外に住んで英語を身につける人を、一人でも多く増やす努力が必要だ。
全日本合宿で英会話教室の実施を
米国の大学で活動し、ノルウェーでコーチを務めた米岡優利恵さん(関連記事)は、残年ながらレスリング界を離れたが(私は戻ってくることを熱望しています)、今年は米国の大学で活動をする選手が男女2人ずついて、日本選手の海外進出の端緒となることを期待したい。
2018年の全日本年末合宿で、松本慎吾・男子グレコローマン強化委員長(当時)が同期で英会話をマスター中だった須藤元気氏(拓大卒=元参議院議員)を呼び、同氏が英会話の必要性を訴え、プチ英会話教室を開く画期的な講習を実施した(関連記事)。
全日本合宿で、前述の米岡さんやマランツさんなどレスリングの国際舞台で活動してきた人の経験談を交えながら、ドーピング講習などのように定期的に英会話教室を実施するのはどうか。選手に英会話の必要性を伝え、英語を学ぶ意欲を高めることも、日本レスリングの発展に必要なことだと思う。
日本代表選手だけではない。選手活動は終わりにするが、将来、レスリング関係の仕事をしたい、という人がいるなら、日本での活動を考えるのではく、世界での活動を考えて海外へ渡ることも視野に入れてほしい。
マット上だけでなく、UWWの中でも世界と堂々と渡り合える日本人の誕生を願いたい。
過去記事
■2025年8月19日:(11)IOCの会長選びに感じる公明正大さ、レスリング協会・会長選出方法の改革を(上)(下)
■2025年7月14日:(10)「大麻クッキー」とは何だ! 読売新聞の暴挙に、徹底抗議するべきだ!
■2025年6月23日:(9)見識が問われる評議員会、ガバナンスコード違反の理事会案を毅然として却下するべきだ!
■2025年6月9日:(8)「密室政治」で会長を決める日本レスリング協会に、未来はあるのか?
■2025年5月17日:(7)「正論」は必ずしも正しくない! 「選手救済」のルールづくりを
■2025年4月24日:(6)99パーセントの努力で手にしたオリンピック金メダル、“努力した天才レスラー”小林孝至
■2025年4月08日:(5)男子グレコローマンのルール改正案に思う
■2025年3月12日:(4)味わい深い言葉が出てこそ一流選手! 話ができない選手は主役になれません!
■2025年2月20日:(3)日本のスターじゃない、世界のスターを目指せ! Akari FUJINAMI
■2025年2月05日:(2)「絶対に見返してやろうと思っていました」…結果を出し、本音をずばり言ってきた権瓶広光君(当時専大)
■2025年1月21日:(1)「あの記事、くだらないですよ!」…胸に突き刺さったオリンピック金メダリスト二世の言葉