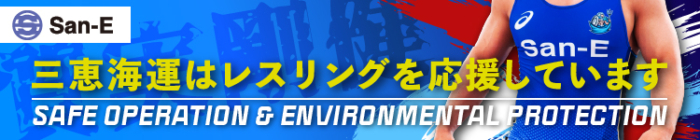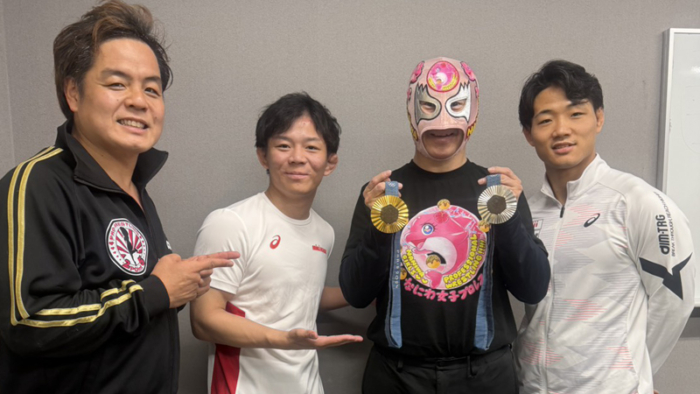【特集】レスリング界に新たな歴史を作れるか、私立から公立に変わった周南公立大の挑戦(下)
遅咲きオリンピック代表選手を輩出した徳山大
徳山大レスリング部は、1972年ミュンヘン&1976年モントリオール・オリンピック代表出同大学教授だった佐藤貞雄氏と後輩の三宅剛氏(ともに大東大卒)が創設。徳山大卒で大学職員となった守田武史氏(1978~81年西日本学生選手権で初の4連覇、1982年全日本選手権2位)がコーチとして助け、同志社大や福岡大とともに西日本大学の雄の一角を占めた。
守田武史監督になってからは、山口・田布施農高時代には全国大会の表彰台がなかった藤村義が2001・03年に西日本学生王者に輝き、自衛隊に進んで全日本王者へ。さらに2012年ロンドン・オリンピックの代表となった。2000年代になって猛威を振るっていた立命館大の10連覇を2006年に阻止したのは、城戸義貴主将(のちに自衛隊で、国体3度優勝)を中心とした徳山大だ(関連記事=日本レスリング協会HP)。
最近では、OBの梅野貴裕が2016年に、堀江耐志が2022年に世界選手権出場を果たしている。ともに高校時代は全国王者のない選手。徳山大でベースをつくり、巣立ってから飛躍した選手だ。
「志(こころざし)だけは変えなかったですね」…守田泰弘監督
守田武史監督の長男の守田泰弘監督は2018年、和歌山県体協勤務から徳山大職員に転職し、チームを見ることになった。日体大時代に学生二冠王(全日本学生選手権、全日本大学選手権)に輝き、卒業後、全日本選抜選手権2位、国際大会優勝(2010年サンキスト・オープン)の経験もある。2018年の全日本選抜選手権まで大会に出場していたので、指導経験はない。「思ったようにできず、学生選手と衝突したこともあります。試行錯誤の連続でしたね」と言う。
日体大でレスリングに取り組んでいた選手として、選手のレベルの違いは、当然、感じたことだろう。父が監督をやっていた頃にも、ときに練習に参加していたし、「選手の技術や意識のレベルが違うことは分かっていたので、驚きはなかったです」と言う。
ただ、「志(こころざし)だけは変えなかったですね」と言う。前年の西日本学生リーグ戦は春季・秋季とも6位だったので、目標は「3年目で優勝、5年以内には学生チャンピオンへ」だった。コロナ禍があったので予定より遅れたが、3年目の秋季に2位、春季が中止となった4年目の2021年の秋季リーグ戦で優勝。翌年の全日本学生選手権で2位の選手が生まれ(永松麗=現自衛隊)、強化は順調に進んだと言える。
永松は高校のとき、全国高校選抜大会もインターハイもベスト8の選手だったが、「トップになりたい、という気持ちが強かった」と言う。永松の代は5人の選手がいたが、そのうちの3人が全日本学生選手権か全日本大学選手権で3位の実績を残した。いずれも高校時代に全国大会のトップには行っていない選手。そうした実績のない選手を「育てた」という自負がある。
連覇の呪縛から解き放された今後が、飛躍のチャンス
だれか一人が上を目指して頑張れば、周囲の選手に伝わり、下級生がそれ見て奮起する、といういい循環が、昨年秋季までの7連覇という結果へ。監督の気持ちも「勝っていくと、欲が出る」そうで、勝つことは、勝負の世界に生きる人間を“依存症”に引きずり込む力があるのだろう。
ただ、7連覇の最中、選手の気持ちが一貫して変わらなかったか、と言えば、そうではない。最初の優勝のときは、選手に達成感とともに「これから」という気持ちがあったが、優勝を重ねるにつれ、満足感というか、「西を制したから、次は東と勝負」という気持ちが芽生えない部分があったのは事実だ。
監督が「目標は全国だよ」と言っても、選手の心のどこかに「西の王者」で満足している面があることを感じたという。もちろん、選手を責めることはできない。連覇のプレッシャーは回数を重ねるごとに強くなり、その重圧を乗り越えることに必死で、全国レベルへの進出にまで気が回らないのも仕方あるまい。
リーグ戦の連覇が途切れたことに無念さがある一方、連覇の呪縛から解き放された今が飛躍のチャンスととらえている。悔しさをエネルギーに変え、東日本の大学に対抗できるチームの育成を目指したいところが、公立大学に変わったことでスカウトが以前とは変わり、これまでとは別の壁に向かわねばならなくなった。「人生は、思うようにいかないですね。どの世界でも同じでしょうけど」と苦笑い。
選手育成の方針は変わらない、最も求めるのは「努力」
だが、徳山大の時代から、無名選手を日本のトップ級に飛躍するベースをつくったチームだけに、スカウト制度が変わろうとも、選手育成の方針は変わらない。もちろん、最も求めるのは「努力」だ。
「卒業してからもレスリングをやる選手ばかりではない、この4年間で、ひとつの目標を目指し、それを達成するために努力したことが卒業後の武器になる。だれもが、あきらめずに、西日本だけではなく全国のトップを目指して頑張ってほしい」
リーグ戦の優勝などのあとは周南市役所に市長を訪れ、報告に行くようにしている。地元メディアが取り上げてくれるのでレスリング部の存在をアピールするためもあるが、きちんとした社会人になってほしいための経験でもある。
「学生時代から、スーツを来て市長と面会する機会を持たせることが、社会人になって役立つ」という思いから。市長が多忙な中でも訪問を受け入れてくれるのは、地元密着チームならではだろう。地元メディアが報じてくれることで、「選手にとっては一生の思い出になるでしょう」とも話す。
いろんな試みに挑みながら、日本レスリング界に公立大学の躍進を目指す。
《完》