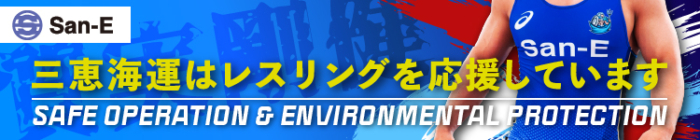【特集】南国・都城市に息づく“レスリングの街”、南九州大が日本の頂点を目指す(上)
レスリングを自治体が支援し、「レスリングの街」となっている市は、全国でいくつかある。大阪・吹田市などは、長年にわたって吹田市民レスリング教室をバックアップ。マットの購入など市を挙げてレスリングを支援している。吉田沙保里さんの出身の三重・津市も、体育館を「サオリーナ」と名付け(愛称ではなく正式名称)、全国有数の大規模大会となっている吉田沙保里杯を主催するなど「レスリングの街」を歩んでいる。
宮崎・都城市も「レスリングの街」へ向けて進んでいる街のひとつ。キッズ・クラブ、高校、大学でレスリング部があり、密接なつながりを持つ。同市はモンゴル・ウランバートルと友好交流都市提携を結んでおり、レスリングの国際交流もしてきた。
一貫強化による今後の発展が期待される都城市にある南九州大を追った。(取材・撮影=保高幸子)
校舎移転で休部、大きなエネルギーをかけて再興
1979年宮崎国体へ向けて、前年の1978年に前監督の西村盛正氏が正式創部した南九州大レスリング部。2010年、校舎が高鍋町から都城市に移転されることになり、練習場所の関係で休部。再興を目指して大学と交渉を続け、1億6,000万円をかけて新しいレスリング場をつくってくれることになったが、資材の高騰などの想定外の事態が次々と起こった。いったん停止したエンジンを再び動かすのは予想以上のエネルギーが必要だった。
だが、西村氏の「もう一度、レスリングの火を灯すんだ」という気持ちは消えなかった。都城市は当時、キッズクラブ(Wellness Kids 都城レスリングクラブ)のほか、都城西高校があって活動しており、部が休止している間の2018年には伊調馨と松永共広、2019年には浜口京子と永田克彦というオリンピアンを呼び、来日したモンゴル選手とキッズ選手・高校選手を相手に合同練習を行うなど、積極的なレスリング活動をしていた。
これも西村氏の気持ちを後押しした。コロナの真っ最中の2020年10月、専大OBの竹田展大氏を監督に迎え、10年の年月を費やしたが部を復活させ、新たなスタートを切った(関連記事)。それは都城市でのキッズから大学までの一貫強化の始まりでもある。
2021年の西日本学生秋季リーグ戦に復活参戦
休部前の南九州大は、西日本学生リーグ戦で最高2位の成績があり、西日本学生王者は14人も輩出した。西村氏による、学生の遠征を含めて日本代表選手として海外へ行った選手は16人いて、国際舞台へも飛躍。日本文理大や九州共立大にレスリング部が創部されるまでは、福岡大とともに九州・沖縄の選手の受け皿のひとつだった。
西村氏は全日本社会人選手権で8度優勝の実績を持ち、全日本マスターズ選手権10度優勝、世界ベテランズ選手権でも優勝できたのは、「強い学生とがんがん練習したからですよ」と振り返る(関連記事)。
そんな強い大学、強い指導者がいても、10年もブランクがあれば、その実績は過去のもの。「部を復活しました」で部員が集まるものではない。レスリング場オープンの前に練習を再開したときの9人の部員は、ほとんどが未経験者だった。
個人戦への出場を経て、2021年12月、高校時代のレスリング経験者が2人という布陣で西日本学生秋季リーグ戦へ臨み、1勝をマークして二部リーグ6位。西村氏は「ようやく、本当の意味でスタートラインに立った。昔は『飴とムチ』で鍛えた。今はそれが難しい時代になっている。若い竹田監督なら、現代に合った指導ができると思う」と、当時29歳の指導者に期待した。
「自分のお母さんにレスリングを教える」という指導
竹田監督は世界ジュニア(現U20)選手権出場もある強豪選手で、東京・WRESTLI-WIN(永田克彦代表)で指導経験を経て南九州大監督へ就任した。もちろんスポーツ推薦枠はない。まず総合選抜型入試で女子選手を入れ、女子での台頭を目指して復活をアピール。それから男子選手の獲得だ。
練習は、朝が約1時間でマットワークの日もある。夕方は約3時間。初心者の多いチームなので、やや長めでやってきた。大学に入ってからレスリングを始めた選手の指導は「キッズ選手と違った難しさがある」とのこと。
その指導方法を例えるなら、「自分のお母さんにレスリングを教える」だそうだ。監督の母は子供のやってるレスリングに関心を示し、「(ローリングは)なんで回るの?」など、よく聞いてきたという。そのときに話したように、ローリングが回る理論を選手に教えることが必要。理論を教えずにやらせても、的確な技をかけることはできない。
専大時代、コーチだった佐藤満・現総監督(1988年ソウル・オリンピック金メダリスト)が“理論の宝庫”で、徹底的に教えられたことが、今、役だっているという。