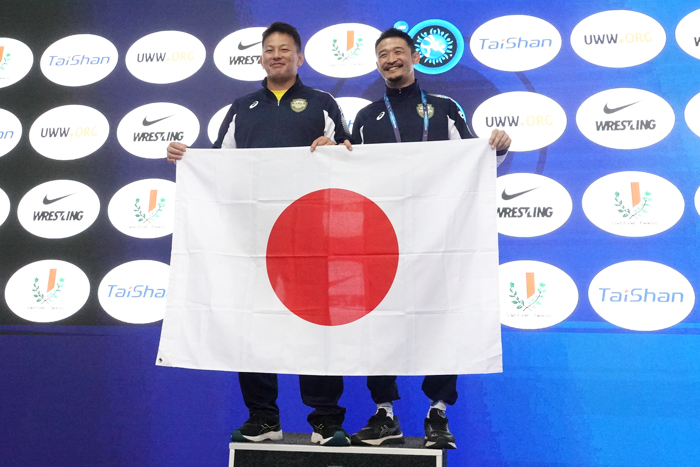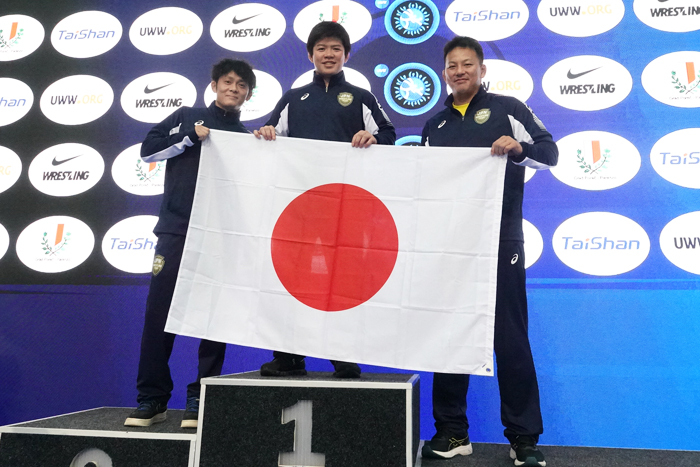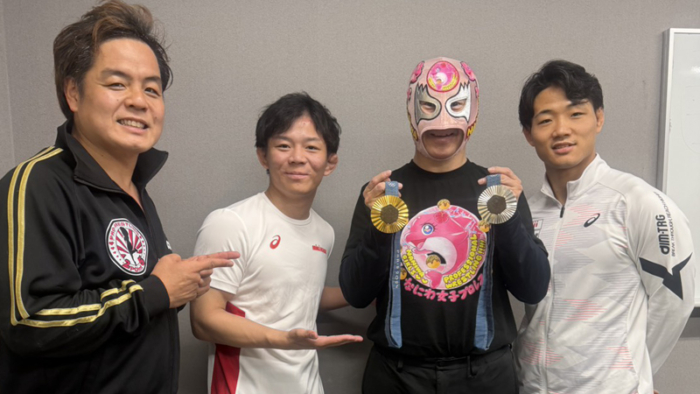【2024年世界ベテランズ選手権・特集(オピニオン)】マット上で展開されている闘いは、まぎれもない“チャンピオン・スポーツ”
※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。
(文・撮影=樋口郁夫)
クロアチア・ポレチュで行われた世界ベテランズ選手権を初めて取材し、感じたことは、この大会はまぎれもなく“チャンピオン・スポーツ”という事実だ。大会に接するまでは、正直なところ、「レスリングの好きな人が、現役時代の残り火を燃やしている大会」というイメージだった。
健康維持のための市民マラソンとまでは思っていなかったが、趣味を同じくする選手の大会であって、勝っても負けても、参加することに価値を見いだしている、という思いを持っていた。闘っている選手の真剣さと、勝利にとことんこだわる姿勢の前に、そのイメージが間違っていたことを思い知らされた。
特に印象深かったのが、Division B(41~45歳)78kg級で優勝した米国選手だ。優勝が決まってマットを下りると号泣。ウォーミングアップ場には戻らず、すぐに観客席へ向かって妻とおぼしき人と抱き合って優勝を喜んでいた。
2ヶ月前に見たパリ・オリンピックに比べれば、観客の数も応援する人もけた違いに少ないし、取材するメディアもいない。米国レスリング協会のホームページが報じる以外、彼の優勝を報じるメディアはないだろう。
彼にとっては、そんなことはどうでもいいのだと思う。世界レスリング連盟(UWW)が認める「World Championships」での優勝が尊いのであり、家族の協力のもとで勝ち取ったまぎれもない世界チャンピオン。ひとつの挑戦を勝ち抜いた事実が、間違いなく人生に残る。
「チャンピオン・スポーツ」の定義とは?
「チャンピオン・スポーツ」の明確な定義はないが、「競技水準を極めることを目標に、全国や世界のひのき舞台での活躍を目指す」「技術や体力の極限に挑む」とするなら、このマットで展開されているレスリングは、間違いなく「チャンピオン・スポーツ」に属するもの。
20代の体力がピークの選手が挑む闘いだけが「チャンピオン・スポーツ」ではない。30代には30代の、40代には40代の…、それぞれの条件のもとで極限に挑むことも、「チャンピオン・スポーツ」以外の何ものでもない。
日本チームの全試合が終わったあと、私は選手に対し、この大会に対して間違ったイメージを持っていたことを詫びるとともに、シニアや若い世代の海外遠征と同じように「日本オリンピック委員会から補助金が出るようにするのが、上に立つ人の役目だと思います」とあいさつした(大きな拍手が起きました)。「チャンピオン・スポーツ」に日本代表として参加する選手に、遠征の際に支援があってしかるべきだと思ったからだ。
世界のスポーツ・イベントに発展したパラリンピック
「チャンピオン・スポーツ」への変貌で私が思い出したのは、パラリンピックの発展だ。大学を卒業して通信社に入った私は、そこで初めてパラリンピックの存在を知ったが、報道は微々たるもの。現地に記者やカメラマンを派遣することはなく、外電が報じる結果の中から好成績の日本選手を抜き出し、20行程度の「短信」記事を書くのが新人の役目だった。
記事を受け取る新聞社も“ベタ記事”(紙面の下の方にある目立たない短い記事)だし、取り上げない新聞社も少なくなかった。
上司に「オリンピック報道と大違いですね」と聞いたところ、「パラリンピックは、スポーツじゃないからね」との答。パラリンピックの起源は戦争で負傷した兵士のリハビリのイベントであり、福祉政策の一環だったから、この答えは必ずしも間違ってはいない。
その後、身体に障がいを持ちながらも挑戦を望む人の熱意と、それを支えるリーダーの力によって、1989年に国際パラリンピック委員会(IPC)が設立され、以後、競技スポーツとして発展。国際オリンピック委員会(IOC)と提携し、現在ではオリンピックに匹敵するイベントになっていることは説明無用だろう。
私に「スポーツじゃない」と話した上司は、すでに鬼籍に入っているが、天国から現在のパラリンピックの発展とメディアの扱いを見て、驚いているのではないか(存命中も、回を重ねるごとに発展していったが…)。
ステータスを高めるために必要な選手と関係者の熱意
40年も経てば、社会の常識や価値観の多くが変わる。「チャンピオン・スポーツ」の定義に、「各年代の最強選手を決める」が加わってもおかしくない。世界ベテランズ選手権に出場する選手の熱意と、それを支援する強烈なリーダーがいれば、この大会がシニアの世界選手権に近いステータスを得ることは可能だと思う。
インターネットなどのコミュニケーション手段の発展によって時代の流れが格段に速くなっている現在、40年と言わず、20年でも実現できるはず。そのためには、30代、40代、50代になっても、シニアの日本トップ選手に引けをとらずに闘える選手が積極的に出場し、大会のレベルを上げることが必要。パリ・オリンピックで大勝利を挙げた日本に、その役目があると言っても過言ではあるまい。
国内予選となる全日本マスターズ選手権は、“市民マラソン”の要素をなくすべきではない。東京マラソンなど世界の主要マラソン大会が、その国の代表選考会を兼ねつつ一般市民にも門戸を開けており、2部門の混合は時代の流れ。“市民選手”の存在は、そのスポーツを支えるパワーとして欠かすことはできない。
その熱きエネルギーが、世界ベテランズ選手権のステータス向上へとつながる。全日本マスターズ連盟の今後の活動に期待したい。