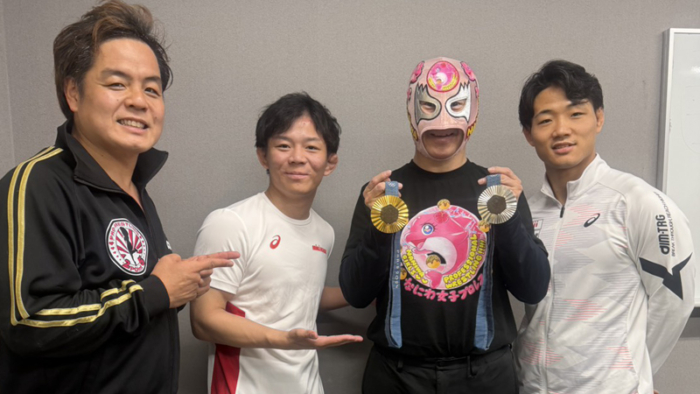【記録】“全国大会出場できず”から頂点に立った加藤喜代美(北海道・旭川商高~専大卒)…オリンピック・日本代表選手
※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。
前回、インターハイ優勝など高校時代の実績は、必ずしもオリンピック代表につながらないことをお伝えした。逆に、高校時代に全国王者のない選手のオリンピックでの活躍をお届けしたい。
一口に全国大会と言っても、以前の高校生の全国大会はインターハイ(1954年スタート)と国体(個人戦は1953年に本格スタート=グレコローマンは1969年スタート)しかなかった。高校入学後にレスリングに取り組むのが普通で、2年半のキャリアでは素質を開花できなくとも、その後に花開いた選手は多く、「全国大会優勝なし」のオリンピアンは数多くいる。
金メダリストでも珍しいことではなく、1964年東京大会の渡辺長武、1968年メキシコ大会の金子正明、宗村宗二、1972年ミュンヘン大会の加藤喜代美、1976年モントリオール大会の高田裕司(現日本協会専務理事)が、高校の全国大会優勝を経験することなくオリンピックの頂点に立っている(他に、柔道からの転向3選手)。
直近の金メダリストである2012年ロンドン大会の米満達弘は、全国高校生グレコローマン選手権と国体グレコローマンで優勝していたものの、フリースタイルでの全国一はなかった。
ただ、全国王者はなくともメダルには手が届いていたのが普通で、大器の片りんは見せていた。唯一の例外が1972年ミュンヘン大会フリースタイル52kg級を制した加藤喜代美(北海道・旭川商高~専大卒)。1964年東京大会の吉田義勝、1968年メキシコ大会の中田茂男と、北海道旭川市出身選手でフリースタイル最軽量級の金メダルを続けたことで有名だが、吉田と中田がインターハイ王者だったのに対し、加藤は北海道2位だった選手。インターハイも国体も出場できなかったところから、オリンピックの頂点に登りつめた。
専大の推薦入試の資格を満たしていたかどうか不明だが、恩師(4月に死去された旭川協会顧問の赤松克則氏)が必死に頼み込み、入学できたという。それだけに、後には引けない思いが強かったようだ。加藤氏は今回の取材に対し、「インターハイで優勝していたら、満足してオリンピック出場はなかったと思います」とも振り返る。
他に、当時の北海道は競争が激しく、道2位でも全国3位は狙えるレベルだったことと、同期にインターハイ団体優勝の青森・八戸高の選手が多く入部し、「ハイレベルの中で鍛えられたことがよかった」と言う。大学2年生で全日本王者に輝くあたりは、レスリング王国・北海道出身者ならではの快挙だろう。《続く》
オリンピック金メダリスト(男子)の高校時代の成績(1964年東京大会以降)
| 選 手 名 | オリンピック優勝の階級 | 出身高校 | 高校時代の主な成績 |
| 米満 達弘 | 2012年フリースタイル66kg級 | 山梨・韮崎工 | インターハイ2位(※1) |
| 佐藤 満 | 1988年フリースタイル52kg級 | 秋田・秋田商 | 高校三冠王(※2) |
| 小林 孝至 | 1988年フリースタイル48kg級 | 茨城・土浦日大 | 高校三冠王(※2) |
| 富山 英明 | 1984年フリースタイル57kg級 | 茨城・土浦日大 | 高校三冠王(※2) |
| 宮原 厚次 | 1984年グレコローマン52kg級 | 鹿児島・岩川 | 柔道からの転向 |
| 伊達治一郎 | 1976年フリースタイル74kg級 | 大分・佐伯農 | インターハイ優勝 |
| 高田 裕司 | 1976年フリースタイル52kg級 | 群馬・大泉 | インターハイ3位 |
| 柳田 英明 | 1972年フリースタイル57kg級 | 秋田・秋田商 | インターハイ優勝 |
| 加藤喜代美 | 1972年フリースタイル52kg級 | 北海道・旭川商 | 北海道2位 |
| 中田 茂男 | 1968年フリースタイル52kg級 | 北海道・旭川南 | インターハイ優勝 |
| 金子 正明 | 1968年フリースタイル63kg級 | 栃木・足利工 | インターハイ2位 |
| 宗村 宗二 | 1967年グレコローマン70kg級 | 新潟・巻農 | インターハイ3位 |
| 市口 政光 | 1964年グレコローマン57kg級 | 大阪・浪速 | 柔道からの転向 |
| 花原 勉 | 1964年グレコローマン52kg級 | 山口・豊浦 | 柔道からの転向 |
| 渡辺 長武 | 1964年フリースタイル63kg級 | 北海道・士別 | インターハイ2位 |
| 上武洋次郎 | 1964・68年フリースタイル57kg級 | 群馬・館林 | インターハイ優勝 |
| 吉田 義勝 | 1964年フリースタイル52kg級 | 北海道・旭川商 | インターハイ優勝 |
(※1)グレコローマンでは全国高校生グレコローマン選手権と国体で優勝。(※2)高校三冠王=全国高校選抜大会、インターハイ、国体